 マインドセット
マインドセット
マインドセットを変える方法!初心者の為のマインドチェンジの教科書
 マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット 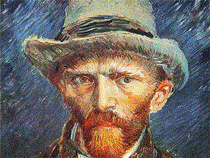 マインドセット
マインドセット 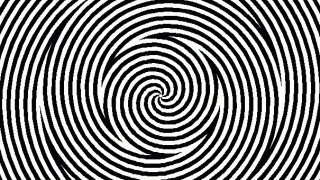 マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット 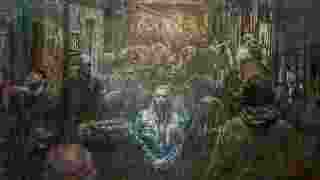 マインドセット
マインドセット  マインドセット
マインドセット  起業・副業
起業・副業 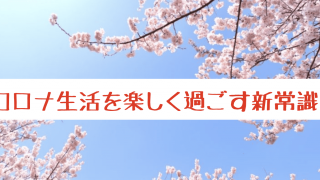 ライフ
ライフ  マインドセット
マインドセット  ライフ
ライフ 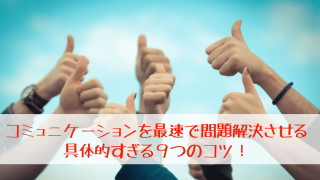 コミュニケーション
コミュニケーション  ライフ
ライフ  マインドセット
マインドセット  コミュニケーション
コミュニケーション  ライフ
ライフ  ライフ
ライフ